| トップページへジャンプ | 刑罰史料館Aへ戻る | 前へ戻る | 次へ進む |
断首刑(装置) |
|||
| 「ギロチン」は欠点の全くない、正確、完璧な機械ではなかった。 運悪く死刑囚の「頭蓋を剥がし」、役人の方を向いて、「もっと下を切った方がよいですか?」と訪ねた死刑執行吏の話はよく知られている。 死刑執行吏助手「ピエール・ロック」は、抵抗する死刑囚の首を押さえつけようとして、自分の指を3本切断してしまった。 (死刑囚の首は無傷) 「サン・ナゼール」では、助手が直前に斬首された死刑囚の首をどけるのを忘れ、次の死刑囚が首穴に頭を入れると、目の前の生首と目があった。 その死刑囚は恐ろしい叫び声を上げて首をすくめたため、顔の中央で切断されてしまった。 |
|||
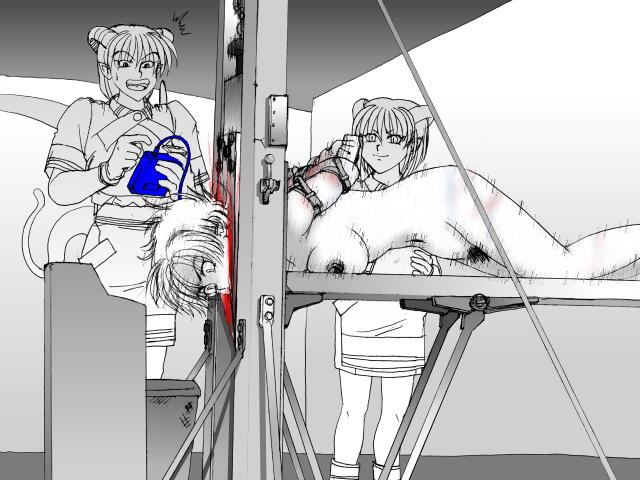 |
|||
| また、3度にわたって刃を落下させたあげく、執行吏が短刀で首を切り離さねばならなかった死刑囚「シャリエ」の事例。 そして、首が太すぎて首穴にハマらなかった、大統領暗殺犯「ゴルグブロフ」の事例なども報告されている。 1792年4月25日、史上初のギロチンによる処刑に膨大な数の人々が立ち会った。 しかし、この群衆は「ギロチン」の見事な効力に驚くとともに、あまりのあっけなさに非常にがっかりしたという。 その失望は、憲兵によって処刑台からかなり離れた位置で見物させられただけになおさら大きかった。 群衆は「木の絞首台を返せ!」と、はやり歌を合唱することでその気持ちを表した。 しかし「犠牲者の身分が、ギロチンを救った」(ジルベール・J・カランドーの言葉。) 人々は、王族、軍人、役人の首がはねられるのをみる度に、「ギロチン」に熱狂していった。 置物、雑貨、家具、皿、など数え切れない品に「ギロチン」や「断頭の場面」が描かれた。 いくつかの商店はシンボルマークにギロチンを用いた。 裁判所では、マホガニー製の「ギロチン」のミニチュアが何百個も売られていた。 「父親、教師などが、子供や生徒を処刑見学に連れて行くことがよくある」と1793年にメルシエ議員が語っている。 ギロチン台の足下には、常に興奮した群衆がいて、死刑囚を罵ったり唾を吐きかけたりした。 人々は、囚人が引き出されてから断頭までの時間を計測したり、死刑執行吏の手腕を批評したりした。 受刑者の苦しみを楽しもうと処刑台のすぐそばに陣取るサディストもいたし、ただふざけている単なる野次馬もいた。 白木のギロチンは「聖母マリア」、赤く塗られたギロチンは「純血を奪われた娘」とよばれた。 「聖ギロチンくじの当選者リスト」(処刑された人間のリスト?)が毎日売られた。 1794年の「エベール」の処刑には40万人の人々が集まったといわれている。 次回の見せ物を人々に知らせるため、触れ役が鳴り物入りで宣伝した。 それは、死刑執行吏たちにとって、新たな栄華の時代だった。 ブルジョワたちも「ギロチンによる血のミサ」に魅了されていた。 パリや、大都市では処刑を口実にして晩餐会、社交パーティーがギロチン処刑台の前で催され、明け方まで続いた。 政府は、その恥知らずな行為の数々の前に、対策を立て始めた。 1870年 処刑台と、そこにあがるための10段のステップが取り除かれ、処刑が見にくくなった。 1878年 ギロチンをアラゴ通りにあるサンテ刑務所の内壁のそばに置き、群衆からギロチンを引き離すことにした。 しかし、上流階級の人間、作家、政治家がギロチンのそばに行く「優遇処置」を要求し、これを獲得していた。 それでも、地方では公開処刑が続けられており、そのため多数の人々が首都から地方へ移動した。 1939年6月24日 政令が発布され、公開処刑が禁止された。 |
|||
断首刑(装置)11「断首刑(装置)12」へ続きます。 |
|||
| トップページへジャンプ | 刑罰史料館Aへ戻る | 前へ戻る | 次へ進む |