| トップページへジャンプ | 刑罰史料館Aへ戻る | 前へ戻る | 次へ進む |
断首刑(装置) |
|||
| ●死刑執行吏 落下距離が2.25メートル、刃の重さが7キロ、重りが30キロ、刃を固定するボルトが3キロとして、合計40キロのギロチンの刃が、囚人の首に到達するときの速度は、摩擦は無視するとして、秒速6.5メートル(時速23.4キロメートル)となる。 また、肉体による抵抗がごく小さいとして、ギロチンが直径13センチの標準的な首を切断する時間は、百分の2秒となる。 つまり、刃が支えから外れて首を切り終わるまで2分の1秒もかからない計算になる。 死刑執行吏たちは、ギロチンの使用法を完全に身につけるとすばらしい働きをし始めた。 |
|||
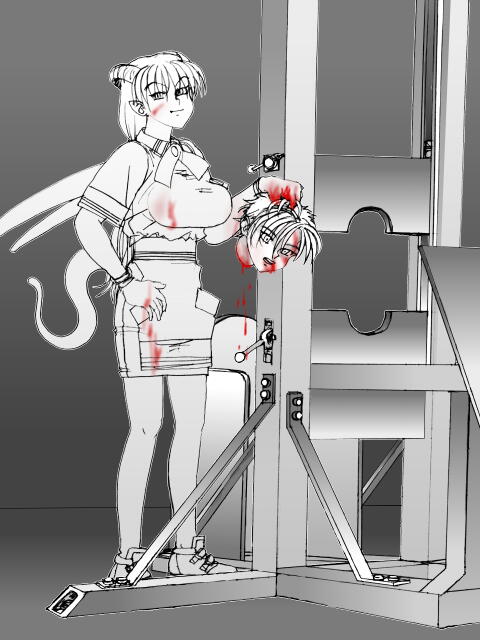 |
|||
| 「大」サンソンこと「シャルル・アンリ・サンソン」は「サンソンとその弟子たちはあまりに素早くギロチンを操作するため、まるで人間隠しの手品を行っているようだ、彼らは13分で12人の首をはねた。」といわれた。 1909年1月18日 パ・ド・カレ県ベチューヌで死刑執行吏「アナトール・デイブレ」は、9分間で4人の頭をはねた。 デイブレは処刑と処刑との間に機械を清掃し、刃に付いた血を拭く労も行ったと言われている。 1956年 フランス公認執行吏「オブレヒト」の助手が「パリ・マッチ」誌の記者「ジャン・ケール」に語った。 「オブレヒトは、毎回時間を計測しました。囚人を確保し、戸口から出し、2段のステップを上らせ、跳ね板の上に押しつけ、刃を始動させるまでにかかった時間は平均6秒から7秒でした。」 フランス領土以外で、ギロチンを採用したのは「ナチスドイツ」のみで、跳ね板のないギロチンを導入していた。 ドイツで、1939年から45年にかけて「ギロチン」が蘇ったのは、迅速さと大量処刑可能というその長所のためであった。 ミュンヘンのシュタデルハイム監獄だけで、1200人以上の断頭が行われた。 1943年9月 ベルリンのプロツェンゼ監獄では、1日に300人の斬首が予定されていた。 しかし、ナチスの執行吏は障害にぶつかった。 それは、機械の不具合や、囚人の態度ではなく、執行吏自身の極度の疲労であった。 疲れ果てた執行吏は、その日の断頭を186人までしか行えず、残り114人の処刑は翌日に延期された。 ギロチンは断頭にめざましい改良をもたらしたが、同時に「死刑執行吏」の世界にもいくらかの混乱をもたらした。 死刑執行吏という職業にとって、もはや止めることの出来ない「衰退」の歴史の始まりであった。 1793年6月 旧体制下のフランスには領有地内に160人の執行吏と400人ほどの助手がいたとされているが、1県に1台のギロチン、1台のギロチンに一人の執行吏を割り当てるという政令がこの年発布され、死刑執行吏の人数は公式には83人に減少した。 1810年 「個人の自由、法の下の平等、私有財産の神聖不可侵」を謳う、いわゆるナポレオン法典(の中の刑法典)の発布後、方は厳格さの度合いをゆるめていき、死刑判決自体が減っていった。 1832年 刑法に「情状酌量」が導入され、いくつかの犯罪に対する死刑が廃止されるとギロチンにかけられる人数はさらに減っていき、死刑執行吏の仕事も縮小し続けていった。 さらに、死刑執行吏の数を半数まで減らすことを目的に「執行吏が死亡や個人的な理由でその職を離れても代わりの執行吏を任命することはない」と規定されるにいたって、死刑執行吏の将来は閉ざされたと言ってよかった。 1849年 政令によって、控訴院を有する県に一人しか死刑執行吏をおかないことが定められ、この時点で執行吏の人数は公式に34人にまで減少した。 1870年11月 政令によって、フランス領域内で職務に就く筆頭執行吏と副執行吏の職を廃することが決定された。 これ以後は、パリの筆頭執行吏と助手5人だけがフランス領土全体における死刑執行の権限を与えられ、ギロチンとともに鉄道で移動して死刑執行を執り行うことになる。 1981年 フランス国民の62%が死刑存続を支持したのにもかかわらず、ミッテラン大統領の「国民の総意を待っていては、いつまで経っても死刑は廃止されない。上からの改革で なければだめだ」との理論の下、死刑廃止が強行された。 そして、フランスにおける死刑執行吏の歴史に幕が下ろされることになった。 |
|||
断首刑(装置)12「断首刑(装置)13」へ続きます。 |
|||
| トップページへジャンプ | 刑罰史料館Aへ戻る | 前へ戻る | 次へ進む |