| トップページへジャンプ | 刑罰史料館Aへ戻る | 前へ戻る | 次へ進む |
断首刑(装置) |
|||
| ●死刑囚の悪夢編 「ギロチン」にかけられた頭が切られた瞬間直ちに生存をやめるというのは確かなことであろうか? ある者は、「脳の血管の血圧が一定に保たれなければ意識はあり得ず、わずかでも血圧が変化すれば意識を失う」、といい、ある者は、「血液の循環が乱れても脳の機能は維持される。」と考えた。 処刑直後に止血剤を使って出血を止め、胴体と頭を正確に縫い合わせ、気付け薬を鼻の下に置くというような実験も行われたが、「顔に表情が戻り瞼が痙攣した」という立会人の証言も、それが死刑囚の意思によって動いたのか、あるいは筋肉反射で収縮しただけなのかは結論が出ていない。 |
|||
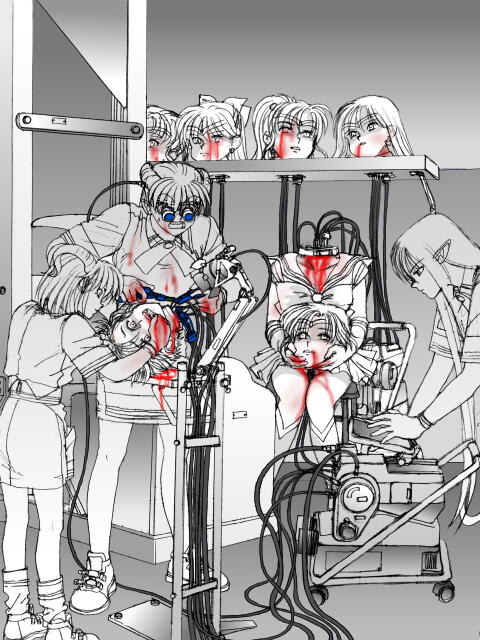 |
|||
| 生化学者の実験によると、齧歯類の首を切断しても数秒間は目を動かしていると言うし、麻酔された羊の場合、頸動脈を2本切断した場合は約14秒、頸動脈と頸静脈を1本ずつ切断した場合は70秒、皮質脳波に断続的な反応が現れた。(1954年グレゴリーとウォトンの論文参照) 脳への血液の供給を止めた犬の場合、12秒後に意識不明となった。(1954年のロバーツの論文参照) 人間の場合は、脳への酸素供給が止まっても、約7秒は代謝を持続させるだけの酸素を蓄えていると考えられる。(1985年のマッキンワインとバチュラードの論文参照) しかし、脳は頭蓋骨内基質や顔、首の筋肉基質からエネルギーを得ている可能性もある。(1947年のタイガーとマニグスの論文を参照) ギロチンで首を斬られた後も、脳が7秒間活動できるだけの酸素が残っているのなら、頭が籠に落ちた後も目が見えて耳も聞こえているとしても不思議ではない。 しかし、人体実験の志願者でも出てこない限り、この問題が解決される見通しはない。 1793年7月 暗殺犯「シャルロット・コルデー」の処刑に立ち会った男の言葉。 「死刑囚の頭部を助手の一人が殴ると、コルデーの顔はまがう事なき怒りの表情を表した。」 1803年 ドイツの「ヴェント医師」が、トレールという死刑囚で行った実験。 「私が急に指を目の前に突き出すと、トレールは瞼を閉じて身を守ろうとした。 また、太陽に向けると、まぶしそうに目を閉じた。 耳元で大声で名前を呼ぶと、閉じかけた目が開き、声のする方へ視線を投げかけ、口も何度か動いた。」 この実験は1分半にわたって行われた。 1804年3月 プロセインでは、斬られた頭部に殺到する科学者の数が処刑ごとに増えていった。 そのため、「フリードリヒ・ウィルヘルム3世」は、政令で「斬首された者の体に関する実験のすべて」を禁止しなければならなかった。 1905年 「ボーリュー」医師と、「ランギル」死刑囚との間である合意が交わされていた。 名前を呼ばれたら、切断された頭で瞼を上下させながら返事をする、という約束だった。 ボーリュー医師の著書より抜粋。 「私は大声で「ランギル!」と呼んだ。すると、生きている人間が見せるような安定した、明快な、正常な動きで瞼がゆっくりとあがった。 数秒後、瞼はゆっくりと閉じたが、私がもう一度名前を呼ぶと、再び瞼がゆっくりと、痙攣もせずに開いた。 そして再び閉じ、私の3回目の声には反応しなかった。すべては、25秒から30秒の出来事だった。」 1953年 「ピエドゥリエーヴル」教授は、医学アカデミーで発表した。 「断頭後、意識は急激に失われる。なぜなら、たとえ筋肉がまだ収縮していても、血液が送られなくなった脳は、数秒で思考機能を失うからである。」 最後に、サンテ刑務所の聴罪司祭で33回の死刑に立ち会った「ドゥボワイヨ」神父の言葉。 「ギロチンの前に置かれた入れ物に頭が落ちた。その死刑囚の瞳が哀願するように私の方に向けられていることをみることができた。 本能的に私は十字を切ってこの頭に神の加護を祈った。すると、その頭は瞬きをし、目の表情が穏やかになった。」 |
|||
断首刑(装置)13●コラム「ジョセフ・イニャース・ギヨタン」ジョセフはイエズス会で教育を受け、ボルドーの修道院で聖職に就くつもりだったが、志望を変更し、当時はるかに人々に必要とされていた医師となったが、後に政界から誘われ、国民議会の議員となった。 生まれつき慈悲深かった彼にとっての懸念は、罪人に科せられる死刑の不公平さと残酷さだった。 これを是正するには、どんな犯罪を犯そうとも、どんな身分であろうとも、死刑は同じ方法で行われなければならないという結論に至った。 当時は斬首が一番速やかに死をもたらすと考えられていたが、いかに熟練した死刑執行吏であろうともミスを犯す、ならば機械によって文字どおり機械的に斬首するべきだと考えた。 ギロチンの誕生である。 基本的な原理に精通しているギヨタン、サンソン、そしてシュミットという名の大工が協力して設計に取り組んだ。 そしてできあがった設計図を、外科学士院長官であり、ルイ16世の顧問外科医を務めていた「アントワーヌ・ルイ」に提出した。 彼らがオフィスで話を詰めているときに王自身もやってきて、図面を見たという話も残っている。 「錠前」作りが趣味だったルイ16世は技術的な問題にも詳しく、刃は「三日月型」ではなく「三角形」つまり刃を斜めにした方がいいと助言した。 王の助言が正しかったことは、9ヶ月後、王自身の首を切断することで証明することになった。 なお、ちまたの噂と違って、ギヨタン自身は「ギロチン」の犠牲になったのではなく、肩に腫瘍ができ、肺炎を併発するというありふれた病を患い、1814年に死亡した。 断頭後の頭部の意識の問題は、臨死体験の話に似ていますが、どちらも体験したくありません。(笑) 「断首刑(装置)」の項は終わりです。 次へ進むと、「絞首刑」に続きます。 |
|||
| トップページへジャンプ | 刑罰史料館Aへ戻る | 前へ戻る | 次へ進む |